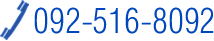第三者認証と関連検査
検査項目に対する規格要求事項
微生物(細菌検査)
 JFS-B規格
JFS-B規格 JFS-G規格
JFS-G規格| 番号 | 項目 | 要求事項 |
|---|---|---|
| HACCP手順2 | 製品情報の記述 | 製品の仕様を文書で作成しなければならない。 その中には、ハザード分析に必要な全ての製品情報を記述しなければならない。HACCPシステムの適用範囲は、製品または製品グループごと、及び製造ラインまたは製造場所ごとに定められていなければならない。
⇒消費期限又は賞味期限の確認(保存試験等) |
| HACCP手順8 (原則3) |
許容限界の設定 | 各重要管理点について妥当性確認された許容限界を設定しなければならない。 ⇒加熱等の基準設定(製造基準より厳しい条件での微生物の挙動確認) |
| HACCP手順11 (原則6) |
HACCPプランの妥当性確認及び検証手順の設定 |
⇒加熱等での許容限界の設定等に問題がないかの確認検査 |
| 番号 | 項目 | 要求事項 |
|---|---|---|
| HACCP-G 手順6・7 (原則1・2) |
危害要因の分析と重要な危害要因の管理方法 | 原材料の仕入れから出荷までの工程の中で、健康被害を引き起こす重要な危害要因を自ら分析を行うか、もしくは適切な方法で特定し、これを管理する方法(どこで何を実施するか)を決めなければならない。 その際には次の6つの工程および、これを管理する方法)を少なくとも考慮に入れなければならない。危害要因としては、生物、化学物質(アレルゲンを含む)、硬質異物を検討しなければならない。 |
| HACCP-G 手順6・7-4 |
加熱・再加熱 | 殺菌を目的とした加熱は、適切な温度と時間による加熱を実施しなければならない。 味・風味のための加熱の場合には、生で食べるものと同じ管理を行わなければならない。 また加熱調理に使用する油は、適切なものを使用しなければならない。 |
| HACCP-G 手順6・7-5 |
冷却 | 加熱した料理等を冷却する場合には、適切な温度と時間による迅速かつ効果的な冷却を実施しなければならない。 |
| HACCP-G 手順11 (原則6) |
検証手順の設定 | 重要な危害要因の管理の方法が、決められた通りに行われているかの確認と取扱いルールの修正の必要性を判断する手順(検証手順)を定めなければならない。検証結果は記録しなければならない。 |
| GMP-G 9 | 交差汚染対策 | 原材料(容器包装資材を含む)、仕掛品、手直し品及び料理の汚染及び交差汚染を防止する手順を整備しなければならない。 汚染源として、微生物、薬剤、アレルゲンなど食品安全のすべての側面を網羅しなければならない。 |
| GMP-G 12 | 清掃・洗浄・殺菌消毒プログラム | 全行程・段階を通じて、整理整頓、清掃、洗浄、必要なところは消毒手順を定め、手順に従って実施し、衛生状態を常に適切な水準に維持しなければならない。 また、清掃道具、洗浄剤及び殺菌剤は意図した目的に即したものを使用し、適切に保管しなければならない。 |
残留農薬分析・残留抗生物質分析
 JFS-B規格
JFS-B規格 JFS-G規格
JFS-G規格| 番号 | 項目 | 要求事項 |
|---|---|---|
| HACCP手順6 (原則1) |
危害要因の分析 |
⇒農産物を主体とした農薬の残留確認・畜産物の抗生物質残留確認 |
| 番号 | 項目 | 要求事項 |
|---|---|---|
| HACCP-G 手順6・7 (原則1・2) |
危害要因の分析と重要な危害要因の管理方法 | 原材料の仕入れから出荷までの工程の中で、健康被害を引き起こす重要な危害要因を自ら分析を行うか、もしくは適切な方法で特定し、これを管理する方法(どこで何を実施するか)を決めなければならない。 その際には次の6つの工程および、これを管理する方法)を少なくとも考慮に入れなければならない。危害要因としては、生物、化学物質(アレルゲンを含む)、硬質異物を検討しなければならない。 |
重金属分析
 JFS-B規格
JFS-B規格 JFS-G規格
JFS-G規格| 番号 | 項目 | 要求事項 |
|---|---|---|
| HACCP手順6 (原則1) |
危害要因の分析 |
⇒農産物を主体とした農薬の残留確認・畜産物の抗生物質残留確認 |
| 番号 | 項目 | 要求事項 |
|---|---|---|
| HACCP-G 手順6・7 (原則1・2) |
危害要因の分析と重要な危害要因の管理方法 | 原材料の仕入れから出荷までの工程の中で、健康被害を引き起こす重要な危害要因を自ら分析を行うか、もしくは適切な方法で特定し、これを管理する方法(どこで何を実施するか)を決めなければならない。 その際には次の6つの工程および、これを管理する方法)を少なくとも考慮に入れなければならない。危害要因としては、生物、化学物質(アレルゲンを含む)、硬質異物を検討しなければならない。 |
食物アレルギー検査
 JFS-B規格
JFS-B規格 JFS-G規格
JFS-G規格| 番号 | 項目 | 要求事項 |
|---|---|---|
| FSM16 | アレルゲンの管理 |
⇒製品でのスクリーニング検査・確認検査等 |
| GMP5 | 従業員用の施設 | 組織は、従業員用の施設はアレルゲンを含めた食品安全のリスクを最小限に抑えられるように設計され、運用されなければならない。 |
| GMP4 | 重要管理点(CCP)では管理できない重要な危害要因の管理(交差汚染の防止) |
|
| 番号 | 項目 | 要求事項 |
|---|---|---|
| GMP-G 7 | 従業員用の施設 | 従業員用の施設はアレルゲンを含めた食品安全のリスクを最小限に抑えるように設計され、運用されなければならない。 |
| GMP-G 9 | 交差汚染対策 | 原材料(容器包装資材を含む)、仕掛品、手直し品及び料理の汚染及び交差汚染を防止する手順を整備しなければならない。汚染源として、微生物、薬剤、アレルゲンなど食品安全のすべての側面を網羅しなければならない。 |
| GMP-G 12 | 清掃・洗浄・殺菌消毒プログラム | 全行程・段階を通じて、整理整頓、清掃、洗浄、必要なところは消毒手順を定め、手順に従って実施し、衛生状態を常に適切な水準に維持しなければならない。また、清掃道具、洗浄剤及び殺菌剤は意図した目的に即したものを使用し、適切に保管しなければならない。 |
異物検査
 JFS-B規格
JFS-B規格 JFS-G規格
JFS-G規格| 番号 | 項目 | 要求事項 |
|---|---|---|
| HACCP手順6 (原則1) |
危害要因の分析 |
|
| HACCP手順10 (原則5) |
是正処置の設定 | 許容範囲を逸脱したものについての是正処置(修正、発生原因の追究及びその原因の除去)の方法を設定しなければならない。
⇒金属探知機やX線探知機をCCPと設定し、異物を検出した場合 |
| GMP13 | 有害生物防御 |
|
| 番号 | 項目 | 要求事項 |
|---|---|---|
| HACCP-G 手順6・7 (原則1・2) |
危害要因の分析と重要な危害要因の管理方法 | 原材料の仕入れから出荷までの工程の中で、健康被害を引き起こす重要な危害要因を自ら分析を行うか、もしくは適切な方法で特定し、これを管理する方法(どこで何を実施するか)を決めなければならない。その際には次の6つの工程および、これを管理する方法)を少なくとも考慮に入れなければならない。危害要因としては、生物、化学物質(アレルゲンを含む)、硬質異物を検討しなければならない。 |
| HACCP-G 手順6・7-4 |
加熱・再加熱 | 殺菌を目的とした加熱は、適切な温度と時間による加熱を実施しなければならない。 味・風味のための加熱の場合には、生で食べるものと同じ管理を行わなければならない。 また加熱調理に使用する油は、適切なものを使用しなければならない。 |
| HACCP-G 手順6・7-5 |
冷却 | 加熱した料理等を冷却する場合には、適切な温度と時間による迅速かつ効果的な冷却を実施しなければならない。 |
| HACCP-G 手順11 (原則6) |
検証手順の設定 | 重要な危害要因の管理の方法が、決められた通りに行われているかの確認と取扱いルールの修正の必要性を判断する手順(検証手順)を定めなければならない。検証結果は記録しなければならない。 |
| GMP-G 9 | 交差汚染対策 | 原材料(容器包装資材を含む)、仕掛品、手直し品及び料理の汚染及び交差汚染を防止する手順を整備しなければならない。 汚染源として、微生物、薬剤、アレルゲンなど食品安全のすべての側面を網羅しなければならない。 |
| GMP-G 12 | 清掃・洗浄・殺菌消毒プログラム | 全行程・段階を通じて、整理整頓、清掃、洗浄、必要なところは消毒手順を定め、手順に従って実施し、衛生状態を常に適切な水準に維持しなければならない。 また、清掃道具、洗浄剤及び殺菌剤は意図した目的に即したものを使用し、適切に保管しなければならない。 |
保菌・検便検査
 JFS-B規格
JFS-B規格 JFS-G規格
JFS-G規格| 番号 | 項目 | 要求事項 |
|---|---|---|
| GMP6 | 従業員等の衛生、 作業服及び健康管理 |
⇒定期的な保菌検査(検便検査)の実施 |
| 番号 | 項目 | 要求事項 |
|---|---|---|
| GMP-G 17 | 食品取扱者等の衛生及び健康管理 | 食品取扱者についての適切な衛生基準を定め、実施しなければならない。 その中には、手洗い方法と頻度、健康状態の確認方法、作業服や履物のルール、調理場への入出方法、食品の取扱方法及び異物混入対策を含めなければならない。 |
ノロウイルス検査
 JFS-B規格
JFS-B規格 JFS-G規格
JFS-G規格| 番号 | 項目 | 要求事項 |
|---|---|---|
| GMP6 | 従業員等の衛生、 作業服及び健康管理 |
⇒定期的なノロウイルス検査の実施 |
| 番号 | 項目 | 要求事項 |
|---|---|---|
| GMP-G 17 | 食品取扱者等の衛生及び健康管理 | 食品取扱者についての適切な衛生基準を定め、実施しなければならない。 その中には、手洗い方法と頻度、健康状態の確認方法、作業服や履物のルール、調理場への入出方法、食品の取扱方法及び異物混入対策を含めなければならない。 |
放射能検査
 JFS-B規格
JFS-B規格 JFS-G規格
JFS-G規格| 番号 | 項目 | 要求事項 |
|---|---|---|
| HACCP手順6 (原則1) |
危害要因の分析 | 各工程における潜在的な危害要因を列挙し、その中から重要な危害要因を特定し、それを管理するためのあらゆる手段を考えなければならない。
危害要因には、必要に応じて、アレルゲンを含めなければならない。
⇒農産物等の放射能検出有無確認 |
| 番号 | 項目 | 要求事項 |
|---|---|---|
| HACCP-G 手順6・7 (原則1・2) |
危害要因の分析と重要な危害要因の管理方法 | 原材料の仕入れから出荷までの工程の中で、健康被害を引き起こす重要な危害要因を自ら分析を行うか、もしくは適切な方法で特定し、これを管理する方法(どこで何を実施するか)を決めなければならない。 その際には次の6つの工程および、これを管理する方法)を少なくとも考慮に入れなければならない。危害要因としては、生物、化学物質(アレルゲンを含む)、硬質異物を検討しなければならない。 |
水質検査
 JFS-B規格
JFS-B規格 JFS-G規格
JFS-G規格| 番号 | 項目 | 要求事項 |
|---|---|---|
| GMP11 | 空気及び水の管理 |
⇒食品衛生法に基づく水質検査の実施 |
| 番号 | 項目 | 要求事項 |
|---|---|---|
| GMP-G 13 | 使用水及び空気(圧縮空気・ガスを含む)の管理 | 食品に使用する水(蒸気と氷を含む)は、用途によって要求する水質基準を定め、定期的にモニタリングし、記録しなければならない。 水を取り扱う施設、器具、及び取扱い方法は、汚染を防止できるものでなければならない。 調理場の空気や使用するガス・蒸気が食品を汚染しないように、微生物対策や臭気及び化学物質対策などの基準を定めて管理する。 |
食品検査室支援サービス
 JFS-B規格
JFS-B規格 JFS-G規格
JFS-G規格| 番号 | 項目 | 要求事項 |
|---|---|---|
| GMP7 | 教育・訓練 |
|
| FSM19 | 検査 |
⇒検査に関連するOJT等 |
| 番号 | 項目 | 要求事項 |
|---|---|---|
| GMP-G 18 | 教育・訓練 | 食品取扱者全員がそれぞれの業務に応じて、食品安全の確保及び実務に関する十分な教育・訓練を受けるよう、責任及び権限に応じた教育訓練プログラム(内容、実施時期、方法、頻度等)を定め、その実施は記録しなければならない。 |